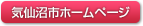録画中継再生
※本会議の録画映像をご覧いただけます。
- 令和4年第129回(12月)定例会 12月12日 本会議 一般質問
- 未来の風 菅原 雄治 議員
eyJwbGF5ZXJLZXkiOiJjYmJlMDljOS0yYzc0LTQwNDEtOWJkNC1iYjZlY2UzYjk0MDAiLCJhbmFseXRpY3NLZXkiOiI5ZWM4YTVlMS1lNWNkLTRkMzUtYTFlMC0wOTE4MWYzOTQwMDYiLCJpc0xpdmUiOmZhbHNlLCJ0aXRsZSI6Imtlc2VubnVtYS1jaXR5XzIwMjIxMjEyXzAwNjBfc3VnYXdhcmEteXV1amkiLCJwbGF5ZXJTZXR0aW5nIjp7InBvc3RlciI6Ii8va2VzZW5udW1hLWNpdHkuc3RyZWFtLmpmaXQuY28uanAvaW1hZ2UvdGh1bWJuYWlsLmZpeC5qcGciLCJzb3VyY2UiOiIvL2tlc2VubnVtYS1jaXR5LnN0cmVhbS5qZml0LmNvLmpwLz90cGw9Y29udGVudHNvdXJjZSZ0aXRsZT1rZXNlbm51bWEtY2l0eV8yMDIyMTIxMl8wMDYwX3N1Z2F3YXJhLXl1dWppJmlzbGl2ZT1mYWxzZSIsImNhcHRpb24iOnsiZW5hYmxlZCI6ImZhbHNlIiwicGF0aCI6IiJ9LCJ0aHVtYm5haWwiOnsiZW5hYmxlZCI6ImZhbHNlIiwicGF0aCI6IiJ9LCJtYXJrZXIiOnsiZW5hYmxlZCI6ImZhbHNlIiwicGF0aCI6IiJ9LCJzcGVlZGNvbnRyb2wiOnsiZW5hYmxlZCI6InRydWUiLCJpdGVtIjpbIjAuNSIsIjAuNzUiLCIxIiwiMS4yNSIsIjEuNSIsIjIiXX0sInNraXAiOnsiZW5hYmxlZCI6InRydWUiLCJpdGVtIjpbMTAsMzBdfSwic3RhcnRvZmZzZXQiOnsiZW5hYmxlZCI6ImZhbHNlIiwidGltZWNvZGUiOjB9LCJzZWVrYmFyIjoidHJ1ZSIsInNkc2NyZWVuIjoiZmFsc2UiLCJ2b2x1bWVtZW1vcnkiOmZhbHNlLCJwbGF5YmFja2ZhaWxzZXR0aW5nIjp7IlN0YWxsUmVzZXRUaW1lIjozMDAwMCwiRXJyb3JSZXNldFRpbWUiOjMwMDAwLCJQbGF5ZXJSZWxvYWRUaW1lIjozMDAwLCJTdGFsbE1heENvdW50IjozLCJFcnJvck1heENvdW50IjozfX0sImFuYWx5dGljc1NldHRpbmciOnsiY3VzdG9tVXNlcklkIjoia2VzZW5udW1hLWNpdHkiLCJ2aWRlb0lkIjoia2VzZW5udW1hLWNpdHlfdm9kXzEwNTEiLCJjdXN0b21EYXRhIjp7ImVudHJ5IjoicHVibGljIn19fQ==
◎一問一答
1 全国学力学習状況調査数値に対する冷静な捉え方とは
(1)石川県の実態から見える過度な学力向上対策に対する本市の考え
全国1位の学力数値を出した石川県の学校現場から「行き過ぎた学力向上対策」というマスコミ報道があった。市民にとっては、数値や順位のみが強調されるため自分たちの県の子供たちが優秀であるという状況だけで評価を高めているその陰に、現場の歪んだ学力向上対策の現実があぶりだされたともいえる。市民は単に子供たちの学力が他県より優秀であるかのような数値で地元の子供たちの現状を満足してしまう傾向が全国的にもあるという。本市においても新聞等の報道を、その視点から捉えてしまい「もっと高い学力を」という社会的な要求を強くしてしまうことも少なからず存在するのではないかと考える。宮城県は長年全国平均を越えない状況が続いているが、もう少し冷静な視点で考える必要がある。「全国平均」を基準数値としている以上、約半数の県がマイナスの評価になることは当然である。どこかの県が伸びれば「平均数値も上がり」どこかの県が落ちることになる。すなわち、そこに過剰な競争原理が働いてしまう。よって、現場への望まぬ負担だけが継続してしまう問題が全国1位の石川県から声が上がったものと感じるのである。この石川県の実態をどのように捉え、本市の教育現場において同様の過度な対策がなされていないのかを伺う
(2)安定した学力を保ち続ける秋田県での行政視察から当局職員が学んできたこと
7月に秋田県秋田市で総務教育常任委員会行政視察を実施した。まさに「学力向上」の先進県秋田において学んできた。秋田県は全国学力学習状況調査が始まった当初(2007年)から群を抜いて高い数値を出していたことから、その取り組みには現在の学習指導要領が目指すべき「探求学習」の指標となる素晴らし教育実践が示されていたと考えられる。私自身も秋田市のその取り組みの効果もさることながら、県民の教育に対する志の高さに大いに感銘を受けてきた。この行政視察において当局職員が学んできたことと、現場の実践に生かすべき内容を伺う
(3)市民が冷静に理解すべき数値の捉え方と、本市が目指すべき学力向上対策への分かりやすい周知方法
市民は、本市が目指すべき学力について、腹を据えた長期的で粘り強い心持が肝要である。そのためには教育委員会と学校が地域住民と共に強い信頼に基づいた経営が不可欠である。その意味で、協働教育に伴うコミュニティ・スクールの確実な意義と、わかりやすい周知の努力が重要であり、その中において気仙沼市が目指す「学力」のベクトルを一致させ、教育現場が安定した実践を持続させる必要性を強く感じる。当局の考えを伺う
2 鹿折地区最大の復興課題「旧大船渡線跡地に関わる諸問題」の解決について
(1)草刈り等の環境整備問題の解決方法
毎年住民から苦情がでる草刈り等の環境整備問題に対し、市とJRが積極的に連携した解決に取り組んでいないように見受けられる。今後の効果的な対策を伺う
(2)大雨によるダム化越水問題の解決方法
JR跡地をくぐる排水路が大雨による流木等によって詰まり、越水による被害の報告が増えてきた。この問題の解決方法を伺う
(3)跡地の利活用問題の解決方法
前述の問題はすべて跡地の利活用をどのようにすすめていくかにかかっている。市は、鹿折地区最大の復興課題の解決に本気で取り組む意思はあるのか。JRに丸投げしているのではないのか。住民の尽きないこの悩みに対し、光が見える答弁を求める
1 全国学力学習状況調査数値に対する冷静な捉え方とは
(1)石川県の実態から見える過度な学力向上対策に対する本市の考え
全国1位の学力数値を出した石川県の学校現場から「行き過ぎた学力向上対策」というマスコミ報道があった。市民にとっては、数値や順位のみが強調されるため自分たちの県の子供たちが優秀であるという状況だけで評価を高めているその陰に、現場の歪んだ学力向上対策の現実があぶりだされたともいえる。市民は単に子供たちの学力が他県より優秀であるかのような数値で地元の子供たちの現状を満足してしまう傾向が全国的にもあるという。本市においても新聞等の報道を、その視点から捉えてしまい「もっと高い学力を」という社会的な要求を強くしてしまうことも少なからず存在するのではないかと考える。宮城県は長年全国平均を越えない状況が続いているが、もう少し冷静な視点で考える必要がある。「全国平均」を基準数値としている以上、約半数の県がマイナスの評価になることは当然である。どこかの県が伸びれば「平均数値も上がり」どこかの県が落ちることになる。すなわち、そこに過剰な競争原理が働いてしまう。よって、現場への望まぬ負担だけが継続してしまう問題が全国1位の石川県から声が上がったものと感じるのである。この石川県の実態をどのように捉え、本市の教育現場において同様の過度な対策がなされていないのかを伺う
(2)安定した学力を保ち続ける秋田県での行政視察から当局職員が学んできたこと
7月に秋田県秋田市で総務教育常任委員会行政視察を実施した。まさに「学力向上」の先進県秋田において学んできた。秋田県は全国学力学習状況調査が始まった当初(2007年)から群を抜いて高い数値を出していたことから、その取り組みには現在の学習指導要領が目指すべき「探求学習」の指標となる素晴らし教育実践が示されていたと考えられる。私自身も秋田市のその取り組みの効果もさることながら、県民の教育に対する志の高さに大いに感銘を受けてきた。この行政視察において当局職員が学んできたことと、現場の実践に生かすべき内容を伺う
(3)市民が冷静に理解すべき数値の捉え方と、本市が目指すべき学力向上対策への分かりやすい周知方法
市民は、本市が目指すべき学力について、腹を据えた長期的で粘り強い心持が肝要である。そのためには教育委員会と学校が地域住民と共に強い信頼に基づいた経営が不可欠である。その意味で、協働教育に伴うコミュニティ・スクールの確実な意義と、わかりやすい周知の努力が重要であり、その中において気仙沼市が目指す「学力」のベクトルを一致させ、教育現場が安定した実践を持続させる必要性を強く感じる。当局の考えを伺う
2 鹿折地区最大の復興課題「旧大船渡線跡地に関わる諸問題」の解決について
(1)草刈り等の環境整備問題の解決方法
毎年住民から苦情がでる草刈り等の環境整備問題に対し、市とJRが積極的に連携した解決に取り組んでいないように見受けられる。今後の効果的な対策を伺う
(2)大雨によるダム化越水問題の解決方法
JR跡地をくぐる排水路が大雨による流木等によって詰まり、越水による被害の報告が増えてきた。この問題の解決方法を伺う
(3)跡地の利活用問題の解決方法
前述の問題はすべて跡地の利活用をどのようにすすめていくかにかかっている。市は、鹿折地区最大の復興課題の解決に本気で取り組む意思はあるのか。JRに丸投げしているのではないのか。住民の尽きないこの悩みに対し、光が見える答弁を求める