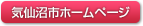録画中継再生
※本会議の録画映像をご覧いただけます。
- 令和5年第130回(2月)定例会 3月1日 本会議 一般質問
- 会派に属さない議員 小野寺 俊朗 議員
eyJwbGF5ZXJLZXkiOiJjYmJlMDljOS0yYzc0LTQwNDEtOWJkNC1iYjZlY2UzYjk0MDAiLCJhbmFseXRpY3NLZXkiOiI5ZWM4YTVlMS1lNWNkLTRkMzUtYTFlMC0wOTE4MWYzOTQwMDYiLCJpc0xpdmUiOmZhbHNlLCJ0aXRsZSI6Imtlc2VubnVtYS1jaXR5XzIwMjMwMzAxXzAwMzBfb25vZGVyYS10b3NoaXJvdSIsInBsYXllclNldHRpbmciOnsicG9zdGVyIjoiLy9rZXNlbm51bWEtY2l0eS5zdHJlYW0uamZpdC5jby5qcC9pbWFnZS90aHVtYm5haWwuZml4LmpwZyIsInNvdXJjZSI6Ii8va2VzZW5udW1hLWNpdHkuc3RyZWFtLmpmaXQuY28uanAvP3RwbD1jb250ZW50c291cmNlJnRpdGxlPWtlc2VubnVtYS1jaXR5XzIwMjMwMzAxXzAwMzBfb25vZGVyYS10b3NoaXJvdSZpc2xpdmU9ZmFsc2UiLCJjYXB0aW9uIjp7ImVuYWJsZWQiOiJmYWxzZSIsInBhdGgiOiIifSwidGh1bWJuYWlsIjp7ImVuYWJsZWQiOiJmYWxzZSIsInBhdGgiOiIifSwibWFya2VyIjp7ImVuYWJsZWQiOiJmYWxzZSIsInBhdGgiOiIifSwic3BlZWRjb250cm9sIjp7ImVuYWJsZWQiOiJ0cnVlIiwiaXRlbSI6WyIwLjUiLCIwLjc1IiwiMSIsIjEuMjUiLCIxLjUiLCIyIl19LCJza2lwIjp7ImVuYWJsZWQiOiJ0cnVlIiwiaXRlbSI6WzEwLDMwXX0sInN0YXJ0b2Zmc2V0Ijp7ImVuYWJsZWQiOiJmYWxzZSIsInRpbWVjb2RlIjowfSwic2Vla2JhciI6InRydWUiLCJzZHNjcmVlbiI6ImZhbHNlIiwidm9sdW1lbWVtb3J5IjpmYWxzZSwicGxheWJhY2tmYWlsc2V0dGluZyI6eyJTdGFsbFJlc2V0VGltZSI6MzAwMDAsIkVycm9yUmVzZXRUaW1lIjozMDAwMCwiUGxheWVyUmVsb2FkVGltZSI6MzAwMCwiU3RhbGxNYXhDb3VudCI6MywiRXJyb3JNYXhDb3VudCI6M319LCJhbmFseXRpY3NTZXR0aW5nIjp7ImN1c3RvbVVzZXJJZCI6Imtlc2VubnVtYS1jaXR5IiwidmlkZW9JZCI6Imtlc2VubnVtYS1jaXR5X3ZvZF8xMDMwIiwiY3VzdG9tRGF0YSI6eyJlbnRyeSI6InB1YmxpYyJ9fX0=
◎一問一答
1 高齢者の転倒予防対策等について
3年ごとに実施されている厚生労働省の国民生活基礎調査では、介護が必要になった主な原因として、「骨折・転倒」が平成13年から平成28年の調査において9.3%から12.1%を占めており、認知症や脳血管障害等に続き第3位から第5位を占めています。転倒による介護リスクの増加を招かないための取り組みについて、以下の点について伺います
(1)介護予防事業にあたり、転倒予防の観点が盛り込まれているか、伺います
(2)高齢者の運動機能向上に向けた事業や講習は行なっているか、伺います
(3)居宅の転倒防止や整理整頓について啓発・支援が行なわれているか、伺います
(4)日本転倒予防学会が制定している10月10日の転倒予防の日に啓発の取り組みを行なうことは検討できませんか伺います
(5)骨粗鬆症が原因で起こる高齢者の骨折の予防について、取り組み状況と啓発について伺います
2 認知機能の低下の予防と支援の取り組みについて
高齢化の進展により認知症高齢者の増加が予測され、その予防が喫緊の課題とされています。認知症を予防するためには、その前段とされる「軽度認知障害(MCI)」や、それ以前の時期に認知機能低下を抑制することが重要であると言われています。そこで、認知機能低下の予防・支援の取り組みについての現状を伺います
3 口腔機能の向上の取り組みについて
腔環境の変化が、要介護認定や死亡のリクスを高めることがあると言われており、口腔機能の向上に関する取り組みが必要と認められています。そこで、本市の取り組み状況を伺います
(1)口腔機能向上の必用性についての周知や学習などの講演会、研修会の実施状況を伺います
(2)歯科衛生士等の専門職による、口腔衛生・口腔機能に関する講座や自主トレーニングの指導等を実施できないか伺います
1 高齢者の転倒予防対策等について
3年ごとに実施されている厚生労働省の国民生活基礎調査では、介護が必要になった主な原因として、「骨折・転倒」が平成13年から平成28年の調査において9.3%から12.1%を占めており、認知症や脳血管障害等に続き第3位から第5位を占めています。転倒による介護リスクの増加を招かないための取り組みについて、以下の点について伺います
(1)介護予防事業にあたり、転倒予防の観点が盛り込まれているか、伺います
(2)高齢者の運動機能向上に向けた事業や講習は行なっているか、伺います
(3)居宅の転倒防止や整理整頓について啓発・支援が行なわれているか、伺います
(4)日本転倒予防学会が制定している10月10日の転倒予防の日に啓発の取り組みを行なうことは検討できませんか伺います
(5)骨粗鬆症が原因で起こる高齢者の骨折の予防について、取り組み状況と啓発について伺います
2 認知機能の低下の予防と支援の取り組みについて
高齢化の進展により認知症高齢者の増加が予測され、その予防が喫緊の課題とされています。認知症を予防するためには、その前段とされる「軽度認知障害(MCI)」や、それ以前の時期に認知機能低下を抑制することが重要であると言われています。そこで、認知機能低下の予防・支援の取り組みについての現状を伺います
3 口腔機能の向上の取り組みについて
腔環境の変化が、要介護認定や死亡のリクスを高めることがあると言われており、口腔機能の向上に関する取り組みが必要と認められています。そこで、本市の取り組み状況を伺います
(1)口腔機能向上の必用性についての周知や学習などの講演会、研修会の実施状況を伺います
(2)歯科衛生士等の専門職による、口腔衛生・口腔機能に関する講座や自主トレーニングの指導等を実施できないか伺います