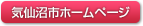録画中継再生
※本会議の録画映像をご覧いただけます。
- 令和6年第143回(12月)定例会 12月16日 本会議 一般質問
- 未来の風 三浦 友幸 議員
eyJwbGF5ZXJLZXkiOiJjYmJlMDljOS0yYzc0LTQwNDEtOWJkNC1iYjZlY2UzYjk0MDAiLCJhbmFseXRpY3NLZXkiOiI5ZWM4YTVlMS1lNWNkLTRkMzUtYTFlMC0wOTE4MWYzOTQwMDYiLCJpc0xpdmUiOmZhbHNlLCJ0aXRsZSI6Imtlc2VubnVtYS1jaXR5XzIwMjQxMjE2XzAwMjBfbWl1cmEtdG9tb3l1a2kiLCJwbGF5ZXJTZXR0aW5nIjp7InBvc3RlciI6Ii8va2VzZW5udW1hLWNpdHkuc3RyZWFtLmpmaXQuY28uanAvaW1hZ2UvdGh1bWJuYWlsLmZpeC5qcGciLCJzb3VyY2UiOiIvL2tlc2VubnVtYS1jaXR5LnN0cmVhbS5qZml0LmNvLmpwLz90cGw9Y29udGVudHNvdXJjZSZ0aXRsZT1rZXNlbm51bWEtY2l0eV8yMDI0MTIxNl8wMDIwX21pdXJhLXRvbW95dWtpJmlzbGl2ZT1mYWxzZSIsImNhcHRpb24iOnsiZW5hYmxlZCI6ImZhbHNlIiwicGF0aCI6IiJ9LCJ0aHVtYm5haWwiOnsiZW5hYmxlZCI6ImZhbHNlIiwicGF0aCI6IiJ9LCJtYXJrZXIiOnsiZW5hYmxlZCI6ImZhbHNlIiwicGF0aCI6IiJ9LCJzcGVlZGNvbnRyb2wiOnsiZW5hYmxlZCI6InRydWUiLCJpdGVtIjpbIjAuNSIsIjAuNzUiLCIxIiwiMS4yNSIsIjEuNSIsIjIiXX0sInNraXAiOnsiZW5hYmxlZCI6InRydWUiLCJpdGVtIjpbMTAsMzBdfSwic3RhcnRvZmZzZXQiOnsiZW5hYmxlZCI6ImZhbHNlIiwidGltZWNvZGUiOjB9LCJzZWVrYmFyIjoidHJ1ZSIsInNkc2NyZWVuIjoiZmFsc2UiLCJ2b2x1bWVtZW1vcnkiOmZhbHNlLCJwbGF5YmFja2ZhaWxzZXR0aW5nIjp7IlN0YWxsUmVzZXRUaW1lIjozMDAwMCwiRXJyb3JSZXNldFRpbWUiOjMwMDAwLCJQbGF5ZXJSZWxvYWRUaW1lIjozMDAwLCJTdGFsbE1heENvdW50IjozLCJFcnJvck1heENvdW50IjozfX0sImFuYWx5dGljc1NldHRpbmciOnsiY3VzdG9tVXNlcklkIjoia2VzZW5udW1hLWNpdHkiLCJ2aWRlb0lkIjoia2VzZW5udW1hLWNpdHlfdm9kXzEzODAiLCJjdXN0b21EYXRhIjp7ImVudHJ5IjoicHVibGljIn19fQ==
◎一問一答
1 持続可能性ついて
(1)サステナ市民会議について
気仙沼市持続可能な社会推進市民会議(サステナ市民会議)は、2023年8月に始まりこれまでワークショップ等を重ねてきましたが、今年6月の第9回分科会から半年が経過します。サステナ市民会議の方向性について市長の考えを伺います
(2)スローフード・スローシティーについて
本市においては震災前にスローフード気仙沼が発行した「まるかじりガイドブック」や、毎年開催している「プチシェフコンテスト」、3年前には「気仙沼スローフェスタ2021」が開催され、昨年10月には「スローなまちづくり全国推進委員会」が結成されています。しかしながら、スローフード・スローシティーに対する市民の理解や認識の広がりがまだ十分とは言えません。以下の点について伺います
①今後、市民の理解を進める取組をどのように行っていくのか伺います
②シティブランドとして外部への発信をどのように進めていくのか伺います
(3)自然共生サイトについて
環境省が実施している「自然共生サイト」は、民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている場所を国が認定する区域のことであり、国立公園などの保護区ではない地域であっても、生物多様性を効果的に保全している地域(OECM)として、国際データベースに登録され、取組のPRや様々な支援のマッチングを誘発などのメリットがあります。生物多様性に対する取組を活性化するため、市政として「自然共生サイト」を生かしていく考えはないか伺います
2 子どもの居場所予算について
本市では「けせんぬまWell-beingプラン2024」や「教育パッケージ」の中で、子どもの居場所づくりを行っている市民団体の経済的支援を謳っています。次年度に向け以下の点について伺います
(1)「子どもの居場所」は多様なケースが想定され、政策の設計が難しいことが予想されます。そこで暫定的な枠組みで事業を実施しながら、1年かけて成案を検討していくことが必要と思われます。市の考えを伺います
(2)国の事業である「地域こどもの生活支援強化事業」を活用することで、各団体への補助の増額や市の負担軽減につながりますが、最終的には教育や他の社会福祉に関する事業と総合的に判断し、子どもの居場所づくりを行っている市民団体の支援を考える必要性があります。市の考えを伺います
3 新型コロナウイルスへの対応について
令和5年5月から新型コロナウイルス感染症の位置づけは、「5類感染症」へと移行し、重症化率も当初に比べ大きく減少している状況ではありますが、市民からはいくつか相談を受けています。以下の点について伺います
(1)本市における近年の新型コロナワクチンの接種状況と予防接種健康被害救済制度の申請数、及びその結果の状況を伺います
(2)気仙沼市立病院の入院患者が、院内で新型コロナウイルスに感染し、そのまま亡くなられた場合の対応について伺います
4 農林道・漁港管理の修繕費について
近年の温暖化による気候変動から豪雨の多発化などにより、災害復旧の対象とならない小さな被害の蓄積により農林道や漁港管理において修繕が必要なケースも増えてきています。以下の点について伺います
(1)市管理の第一種漁港は31港であるが、農林道の各路線数と総延長距離、そして市管理漁港、農道、林道の修繕費の過去5年間の推移を伺います
(2)突発的な被害に迅速に対応するための農林道や漁港管理の修繕費の考え方を伺います
1 持続可能性ついて
(1)サステナ市民会議について
気仙沼市持続可能な社会推進市民会議(サステナ市民会議)は、2023年8月に始まりこれまでワークショップ等を重ねてきましたが、今年6月の第9回分科会から半年が経過します。サステナ市民会議の方向性について市長の考えを伺います
(2)スローフード・スローシティーについて
本市においては震災前にスローフード気仙沼が発行した「まるかじりガイドブック」や、毎年開催している「プチシェフコンテスト」、3年前には「気仙沼スローフェスタ2021」が開催され、昨年10月には「スローなまちづくり全国推進委員会」が結成されています。しかしながら、スローフード・スローシティーに対する市民の理解や認識の広がりがまだ十分とは言えません。以下の点について伺います
①今後、市民の理解を進める取組をどのように行っていくのか伺います
②シティブランドとして外部への発信をどのように進めていくのか伺います
(3)自然共生サイトについて
環境省が実施している「自然共生サイト」は、民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている場所を国が認定する区域のことであり、国立公園などの保護区ではない地域であっても、生物多様性を効果的に保全している地域(OECM)として、国際データベースに登録され、取組のPRや様々な支援のマッチングを誘発などのメリットがあります。生物多様性に対する取組を活性化するため、市政として「自然共生サイト」を生かしていく考えはないか伺います
2 子どもの居場所予算について
本市では「けせんぬまWell-beingプラン2024」や「教育パッケージ」の中で、子どもの居場所づくりを行っている市民団体の経済的支援を謳っています。次年度に向け以下の点について伺います
(1)「子どもの居場所」は多様なケースが想定され、政策の設計が難しいことが予想されます。そこで暫定的な枠組みで事業を実施しながら、1年かけて成案を検討していくことが必要と思われます。市の考えを伺います
(2)国の事業である「地域こどもの生活支援強化事業」を活用することで、各団体への補助の増額や市の負担軽減につながりますが、最終的には教育や他の社会福祉に関する事業と総合的に判断し、子どもの居場所づくりを行っている市民団体の支援を考える必要性があります。市の考えを伺います
3 新型コロナウイルスへの対応について
令和5年5月から新型コロナウイルス感染症の位置づけは、「5類感染症」へと移行し、重症化率も当初に比べ大きく減少している状況ではありますが、市民からはいくつか相談を受けています。以下の点について伺います
(1)本市における近年の新型コロナワクチンの接種状況と予防接種健康被害救済制度の申請数、及びその結果の状況を伺います
(2)気仙沼市立病院の入院患者が、院内で新型コロナウイルスに感染し、そのまま亡くなられた場合の対応について伺います
4 農林道・漁港管理の修繕費について
近年の温暖化による気候変動から豪雨の多発化などにより、災害復旧の対象とならない小さな被害の蓄積により農林道や漁港管理において修繕が必要なケースも増えてきています。以下の点について伺います
(1)市管理の第一種漁港は31港であるが、農林道の各路線数と総延長距離、そして市管理漁港、農道、林道の修繕費の過去5年間の推移を伺います
(2)突発的な被害に迅速に対応するための農林道や漁港管理の修繕費の考え方を伺います