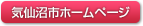録画中継再生
※本会議の録画映像をご覧いただけます。
- 令和6年第143回(12月)定例会 12月16日 本会議 一般質問
- 未来の風 今川 悟 議員
eyJwbGF5ZXJLZXkiOiJjYmJlMDljOS0yYzc0LTQwNDEtOWJkNC1iYjZlY2UzYjk0MDAiLCJhbmFseXRpY3NLZXkiOiI5ZWM4YTVlMS1lNWNkLTRkMzUtYTFlMC0wOTE4MWYzOTQwMDYiLCJpc0xpdmUiOmZhbHNlLCJ0aXRsZSI6Imtlc2VubnVtYS1jaXR5XzIwMjQxMjE2XzAwNDBfaW1ha2F3YS1zYXRvcnUiLCJwbGF5ZXJTZXR0aW5nIjp7InBvc3RlciI6Ii8va2VzZW5udW1hLWNpdHkuc3RyZWFtLmpmaXQuY28uanAvaW1hZ2UvdGh1bWJuYWlsLmZpeC5qcGciLCJzb3VyY2UiOiIvL2tlc2VubnVtYS1jaXR5LnN0cmVhbS5qZml0LmNvLmpwLz90cGw9Y29udGVudHNvdXJjZSZ0aXRsZT1rZXNlbm51bWEtY2l0eV8yMDI0MTIxNl8wMDQwX2ltYWthd2Etc2F0b3J1JmlzbGl2ZT1mYWxzZSIsImNhcHRpb24iOnsiZW5hYmxlZCI6ImZhbHNlIiwicGF0aCI6IiJ9LCJ0aHVtYm5haWwiOnsiZW5hYmxlZCI6ImZhbHNlIiwicGF0aCI6IiJ9LCJtYXJrZXIiOnsiZW5hYmxlZCI6ImZhbHNlIiwicGF0aCI6IiJ9LCJzcGVlZGNvbnRyb2wiOnsiZW5hYmxlZCI6InRydWUiLCJpdGVtIjpbIjAuNSIsIjAuNzUiLCIxIiwiMS4yNSIsIjEuNSIsIjIiXX0sInNraXAiOnsiZW5hYmxlZCI6InRydWUiLCJpdGVtIjpbMTAsMzBdfSwic3RhcnRvZmZzZXQiOnsiZW5hYmxlZCI6ImZhbHNlIiwidGltZWNvZGUiOjB9LCJzZWVrYmFyIjoidHJ1ZSIsInNkc2NyZWVuIjoiZmFsc2UiLCJ2b2x1bWVtZW1vcnkiOmZhbHNlLCJwbGF5YmFja2ZhaWxzZXR0aW5nIjp7IlN0YWxsUmVzZXRUaW1lIjozMDAwMCwiRXJyb3JSZXNldFRpbWUiOjMwMDAwLCJQbGF5ZXJSZWxvYWRUaW1lIjozMDAwLCJTdGFsbE1heENvdW50IjozLCJFcnJvck1heENvdW50IjozfX0sImFuYWx5dGljc1NldHRpbmciOnsiY3VzdG9tVXNlcklkIjoia2VzZW5udW1hLWNpdHkiLCJ2aWRlb0lkIjoia2VzZW5udW1hLWNpdHlfdm9kXzEzODEiLCJjdXN0b21EYXRhIjp7ImVudHJ5IjoicHVibGljIn19fQ==
◎一問一答
1 集会施設における官民格差の解消について
市町合併後、市内にある集会施設において、自治組織所有と気仙沼市所有の施設について、整備費や維持管理費についての格差が課題になっていました。震災復興によって市所有施設が増え、さらに市政懇談会で本吉地域の市所有集会施設の施設更新と会議室へのエアコン設置という新たな方針が示され、その格差はさらに広がることが心配されますので、次の4点について質問します
(1)市が所有する本吉地域の集会施設について、唐桑地域の施設整備後となる令和10年度以降に他の老朽化施設と合わせ、優先順位を決めたうえで順次整備する方針が、市政懇談会で示されました。旧本吉町時代の集会施設は地元が建設費の2割を負担する形で整備されましたが、今後は地元負担を撤廃することになっています。旧本吉町に合わせて制度設計した自治組織所有施設に対する新築・改築の補助率10分の8について、その制度案が示された平成26年6月の東日本大震災調査特別委員会で、これが最終段階であるか確認した際、市当局からは「いくつかのステップの中の一つだと思う。どのような形にしていくのかはこれからの話し合いになると思う」との答弁がありました。増築・修繕等の補助率3分の1と合わせて、公平性確保の観点から見直す時期に来たと思いますが、市の考えを伺います
(2)市所有の集会施設は指定管理者制度を導入して、年間10万円前後の維持管理費分を市から支出していることから、自治組織所有の集会施設に対しても同程度の支援を検討すべきだと思います。自治組織所有の集会施設における維持管理に関する課題と格差の解消について、市の考えを伺います
(3)本吉地域の市所有集会施設では、暑さ対策として会議室にエアコン設置する方針が示されました。一方で、自治組織所有の集会施設のエアコン設置の補助率は3分の1となっており、公平性の観点から補助率を見直すことについて、市の考えを伺います
(4)市公共施設等総合管理計画に基づいて令和2年に策定した個別施設計画では、市の集会施設について地元自治組織への譲渡を検討するとともに、本吉地域の施設は令和8年度から11年度にかけて大規模改修で対応する計画内容となっており、29施設うち19施設で計約11億円の事業費を想定しています。新築も認めるという新たな方針に合わせて個別施設計画を見直さなければなりませんが、官民格差の是正をはじめ、持続可能な指定管理の在り方、公民館の多機能化による集会施設の再編促進策について、将来を見据えた指針も策定すべきと思いますので、市の考えを伺います。そもそも地域コミュニティと地域防災力の向上を目的としている集会施設について、市所有と自治組織所有で何が違い、なぜ格差を是正しようとしないのかについても伺います
2 公共交通と交通弱者対策について
人口に関する課題は少子化だけではなく、高齢化社会についても新たな発想と取り組みが必要になっています。特に公共交通については、総合的な視点による政策立案が求められています。そこで、新たな議論の展開を期待して、次の4点について質問します
(1)市政懇談会では、半分以上の地区で「公共交通」「交通弱者」が地域課題として挙げられました。地域は高齢者が安心して運転免許を返納し、通院や買い物、コミュニティ活動において不便がないような政策を期待しているのに対し、市からの回答は路線バス再編やデマンド交通に関して経費節減の視点が強く、その温度差を感じました。地域の交通問題について、公共交通の観点だけでなく、福祉やコミュニティなど多様な観点から政策を立案することが必要だと思いますが、地域公共交通会議は手続きの場となっており、新たな協議の場と統括的な役割が必要です。市政懇談会の感想を含めて、市の考えを伺います
(2)路線バスの再編や車両のサイズダウンは、毎年10月の契約更新に向けて協議されているとのことですが、最新の契約の見直し内容、次の契約へ向けた見通しを伺います。また、同じく10月に契約更新している市内循環バスについて、ルートの延伸を求められた市政懇談会ではルートや運賃、所要時間、運行経費など、メリットやデメリットを精査して、引き続き検討していく方針が示されましたが、その検討組織、スケジュールを伺います
(3)路線バスの経費は削減が進むどころか、燃油高や人手不足対策などによって膨らむばかりですが、利用者が極端に少ない路線もあり、行財政改革の視点から路線の再編を進めなければなりません。そのためには、他自治体のように収支率や利用者数などで判断する「運行継続基準」を設定することが必要だと思いますので、市の考えを伺います
(4)市政懇談会でも話題となった乗合いを基本とするデマンド交通の課題と、地域での助け合いによる自家用車有償旅客運送の可能性について、市の考え方を伺います。なお、本市の状況からすると、安心して運転免許を返納できるように、まずは交通弱者に対するタクシー補助について可能性を模索すべきだと思いますが、市政懇談会では「財政負担も大きく困難な状況である」と答えています。タクシー補助に関する検討内容と今後の可能性についても伺います
1 集会施設における官民格差の解消について
市町合併後、市内にある集会施設において、自治組織所有と気仙沼市所有の施設について、整備費や維持管理費についての格差が課題になっていました。震災復興によって市所有施設が増え、さらに市政懇談会で本吉地域の市所有集会施設の施設更新と会議室へのエアコン設置という新たな方針が示され、その格差はさらに広がることが心配されますので、次の4点について質問します
(1)市が所有する本吉地域の集会施設について、唐桑地域の施設整備後となる令和10年度以降に他の老朽化施設と合わせ、優先順位を決めたうえで順次整備する方針が、市政懇談会で示されました。旧本吉町時代の集会施設は地元が建設費の2割を負担する形で整備されましたが、今後は地元負担を撤廃することになっています。旧本吉町に合わせて制度設計した自治組織所有施設に対する新築・改築の補助率10分の8について、その制度案が示された平成26年6月の東日本大震災調査特別委員会で、これが最終段階であるか確認した際、市当局からは「いくつかのステップの中の一つだと思う。どのような形にしていくのかはこれからの話し合いになると思う」との答弁がありました。増築・修繕等の補助率3分の1と合わせて、公平性確保の観点から見直す時期に来たと思いますが、市の考えを伺います
(2)市所有の集会施設は指定管理者制度を導入して、年間10万円前後の維持管理費分を市から支出していることから、自治組織所有の集会施設に対しても同程度の支援を検討すべきだと思います。自治組織所有の集会施設における維持管理に関する課題と格差の解消について、市の考えを伺います
(3)本吉地域の市所有集会施設では、暑さ対策として会議室にエアコン設置する方針が示されました。一方で、自治組織所有の集会施設のエアコン設置の補助率は3分の1となっており、公平性の観点から補助率を見直すことについて、市の考えを伺います
(4)市公共施設等総合管理計画に基づいて令和2年に策定した個別施設計画では、市の集会施設について地元自治組織への譲渡を検討するとともに、本吉地域の施設は令和8年度から11年度にかけて大規模改修で対応する計画内容となっており、29施設うち19施設で計約11億円の事業費を想定しています。新築も認めるという新たな方針に合わせて個別施設計画を見直さなければなりませんが、官民格差の是正をはじめ、持続可能な指定管理の在り方、公民館の多機能化による集会施設の再編促進策について、将来を見据えた指針も策定すべきと思いますので、市の考えを伺います。そもそも地域コミュニティと地域防災力の向上を目的としている集会施設について、市所有と自治組織所有で何が違い、なぜ格差を是正しようとしないのかについても伺います
2 公共交通と交通弱者対策について
人口に関する課題は少子化だけではなく、高齢化社会についても新たな発想と取り組みが必要になっています。特に公共交通については、総合的な視点による政策立案が求められています。そこで、新たな議論の展開を期待して、次の4点について質問します
(1)市政懇談会では、半分以上の地区で「公共交通」「交通弱者」が地域課題として挙げられました。地域は高齢者が安心して運転免許を返納し、通院や買い物、コミュニティ活動において不便がないような政策を期待しているのに対し、市からの回答は路線バス再編やデマンド交通に関して経費節減の視点が強く、その温度差を感じました。地域の交通問題について、公共交通の観点だけでなく、福祉やコミュニティなど多様な観点から政策を立案することが必要だと思いますが、地域公共交通会議は手続きの場となっており、新たな協議の場と統括的な役割が必要です。市政懇談会の感想を含めて、市の考えを伺います
(2)路線バスの再編や車両のサイズダウンは、毎年10月の契約更新に向けて協議されているとのことですが、最新の契約の見直し内容、次の契約へ向けた見通しを伺います。また、同じく10月に契約更新している市内循環バスについて、ルートの延伸を求められた市政懇談会ではルートや運賃、所要時間、運行経費など、メリットやデメリットを精査して、引き続き検討していく方針が示されましたが、その検討組織、スケジュールを伺います
(3)路線バスの経費は削減が進むどころか、燃油高や人手不足対策などによって膨らむばかりですが、利用者が極端に少ない路線もあり、行財政改革の視点から路線の再編を進めなければなりません。そのためには、他自治体のように収支率や利用者数などで判断する「運行継続基準」を設定することが必要だと思いますので、市の考えを伺います
(4)市政懇談会でも話題となった乗合いを基本とするデマンド交通の課題と、地域での助け合いによる自家用車有償旅客運送の可能性について、市の考え方を伺います。なお、本市の状況からすると、安心して運転免許を返納できるように、まずは交通弱者に対するタクシー補助について可能性を模索すべきだと思いますが、市政懇談会では「財政負担も大きく困難な状況である」と答えています。タクシー補助に関する検討内容と今後の可能性についても伺います