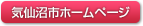録画中継再生
※本会議の録画映像をご覧いただけます。
- 令和7年第144回(2月)定例会 2月26日 本会議 一般質問
- 未来の風 今川 悟 議員
eyJwbGF5ZXJLZXkiOiJjYmJlMDljOS0yYzc0LTQwNDEtOWJkNC1iYjZlY2UzYjk0MDAiLCJhbmFseXRpY3NLZXkiOiI5ZWM4YTVlMS1lNWNkLTRkMzUtYTFlMC0wOTE4MWYzOTQwMDYiLCJpc0xpdmUiOmZhbHNlLCJ0aXRsZSI6Imtlc2VubnVtYS1jaXR5XzIwMjUwMjI2XzAwMzBfaW1ha2F3YS1zYXRvcnUiLCJwbGF5ZXJTZXR0aW5nIjp7InBvc3RlciI6Ii8va2VzZW5udW1hLWNpdHkuc3RyZWFtLmpmaXQuY28uanAvaW1hZ2UvdGh1bWJuYWlsLmZpeC5qcGciLCJzb3VyY2UiOiIvL2tlc2VubnVtYS1jaXR5LnN0cmVhbS5qZml0LmNvLmpwLz90cGw9Y29udGVudHNvdXJjZSZ0aXRsZT1rZXNlbm51bWEtY2l0eV8yMDI1MDIyNl8wMDMwX2ltYWthd2Etc2F0b3J1JmlzbGl2ZT1mYWxzZSIsImNhcHRpb24iOnsiZW5hYmxlZCI6ImZhbHNlIiwicGF0aCI6IiJ9LCJ0aHVtYm5haWwiOnsiZW5hYmxlZCI6ImZhbHNlIiwicGF0aCI6IiJ9LCJtYXJrZXIiOnsiZW5hYmxlZCI6ImZhbHNlIiwicGF0aCI6IiJ9LCJzcGVlZGNvbnRyb2wiOnsiZW5hYmxlZCI6InRydWUiLCJpdGVtIjpbIjAuNSIsIjAuNzUiLCIxIiwiMS4yNSIsIjEuNSIsIjIiXX0sInNraXAiOnsiZW5hYmxlZCI6InRydWUiLCJpdGVtIjpbMTAsMzBdfSwic3RhcnRvZmZzZXQiOnsiZW5hYmxlZCI6ImZhbHNlIiwidGltZWNvZGUiOjB9LCJzZWVrYmFyIjoidHJ1ZSIsInNkc2NyZWVuIjoiZmFsc2UiLCJ2b2x1bWVtZW1vcnkiOmZhbHNlLCJwbGF5YmFja2ZhaWxzZXR0aW5nIjp7IlN0YWxsUmVzZXRUaW1lIjozMDAwMCwiRXJyb3JSZXNldFRpbWUiOjMwMDAwLCJQbGF5ZXJSZWxvYWRUaW1lIjozMDAwLCJTdGFsbE1heENvdW50IjozLCJFcnJvck1heENvdW50IjozfX0sImFuYWx5dGljc1NldHRpbmciOnsiY3VzdG9tVXNlcklkIjoia2VzZW5udW1hLWNpdHkiLCJ2aWRlb0lkIjoia2VzZW5udW1hLWNpdHlfdm9kXzEzOTYiLCJjdXN0b21EYXRhIjp7ImVudHJ5IjoicHVibGljIn19fQ==
◎一問一答
1 震災伝承について
令和8年には東日本大震災から15年の節目を迎えます。犠牲者を追悼するとともに、内外に向けて震災の教訓を伝え、復興に感謝する機会であることから、この1年間の取組が重要になります。未来の命を守るため、次の2点について質問します
(1)東日本大震災遺構・伝承館を拠点とした伝承活動と施設の維持補修のために、ふるさと納税のクラウドファンディングを続け、これまで4億円を超える寄附が集まりました。この寄附金を活用して、伝承館の展示物リニューアルなどに取り組むタイミングだと思います。できれば、市民を巻き込んで、その過程もPRするなど、興味・関心を高める仕掛けづくりも必要です。今後の伝承館の在り方、クラウドファンディングの継続と活用方法について市の考えを伺います
(2)震災の経験と教訓を後世に伝えていくため、今後必要なこととして、①視察や研究などの受け入れ環境の整備②伝承用の資料や教材の作成③海の市など観光施設における展示④復興祈念公園の利活用⑤図書館の震災関連資料の整理と活用などが考えられます。まずは役割分担や推進体制を確認し、総合的な仕組みづくりからスタートすることが必要です。せめて地元の子どもには、高校を卒業するまでに震災と復興の最低限の知識を得てほしいと考えています。岩手県大船渡市は、津波伝承や防災学習の考え方を整理し、ネットワーク形成のための基本計画を策定しており、本市の参考になる事例です。震災15年に向けた震災伝承の取組と課題、仕組みづくりの必要性、そして今後の展望を伺います
2 小・中学校再編の進め方について
令和6年6月に設置した気仙沼市小中学校再編検討委員会が中間報告の取りまとめ作業に入り、具体的な再編案について保護者や市民から意見聴取する段階に進む見込みとなりました。再編計画の決定に向けて重要な局面に入ることから、建設的な議論に発展することを期待して、次の5点について市の考えを伺います
(1)気仙沼市小中学校再編検討委員会に諮問したのは、「再編の基本的な考え方」「具体的な学校配置案」「今次再編後の考え方」「再編整備の具体的な方策」「その他の必要事項」の5項目です。中間報告は3月中に取りまとめる予定ですが、検討委員会を傍聴していて「今次再編後の考え方」と「再編整備の具体的な方策」について議論が不足していると感じました。この2項目を諮問事項に入れた理由と現在の検討状況を伺います
(2)事務局がたたき台として示した中学校を4校に再編する配置案について、検討委員会は「妥当」としましたが、最短で令和9年度、10年度と想定する時期については準備期間への不安から慎重論も出ています。特に階上、面瀬、松岩の3中学校の再編については、1学年最大5クラスと現校舎に入りきらない規模であり、仮設校舎などのデメリットの面も心配されることから、段階的な再編の可能性を含めた慎重な検討が求められます。4月以降に保護者や地域へ説明する際の注目ポイントにもなりますので、「3校同時再編」と「段階的な再編」について教育委員会が考えるメリットとデメリットを伺います
(3)小・中学校の再編の議論と並行して、スクールバスをはじめとする通学費用について、市がどこまで覚悟できるか示していく考えが明らかにされていましたが、中間報告には間に合いますか。現在の検討状況について伺います
(4)合意形成に時間と労力を要した前再編計画の教訓は、計画策定の段階で市民の理解をしっかりと得て、決まったらなるべく早く実行に移すとのことでした。理解を得るためには、メリットだけでなくデメリットについても整理して十分な検討材料を揃えること、再編ではなくても解決できることを混同させないこと、地域への影響について考慮すること、意見を出しやすい環境をつくること、住民同士で話し合いの機会をつくることが大切だと思います。市民理解の醸成に向けた取組と考え方を伺います
(5)中学校を4校に再編することが現実となれば、道路をはじめとするインフラ整備、交通・住宅政策、地域コミュニティにも影響を及ぼすことが考えられます。小中学校再編計画の策定作業と並行して、学校教育以外への影響と今後の対応について考える場が必要と思いますが、市の考えを伺います
1 震災伝承について
令和8年には東日本大震災から15年の節目を迎えます。犠牲者を追悼するとともに、内外に向けて震災の教訓を伝え、復興に感謝する機会であることから、この1年間の取組が重要になります。未来の命を守るため、次の2点について質問します
(1)東日本大震災遺構・伝承館を拠点とした伝承活動と施設の維持補修のために、ふるさと納税のクラウドファンディングを続け、これまで4億円を超える寄附が集まりました。この寄附金を活用して、伝承館の展示物リニューアルなどに取り組むタイミングだと思います。できれば、市民を巻き込んで、その過程もPRするなど、興味・関心を高める仕掛けづくりも必要です。今後の伝承館の在り方、クラウドファンディングの継続と活用方法について市の考えを伺います
(2)震災の経験と教訓を後世に伝えていくため、今後必要なこととして、①視察や研究などの受け入れ環境の整備②伝承用の資料や教材の作成③海の市など観光施設における展示④復興祈念公園の利活用⑤図書館の震災関連資料の整理と活用などが考えられます。まずは役割分担や推進体制を確認し、総合的な仕組みづくりからスタートすることが必要です。せめて地元の子どもには、高校を卒業するまでに震災と復興の最低限の知識を得てほしいと考えています。岩手県大船渡市は、津波伝承や防災学習の考え方を整理し、ネットワーク形成のための基本計画を策定しており、本市の参考になる事例です。震災15年に向けた震災伝承の取組と課題、仕組みづくりの必要性、そして今後の展望を伺います
2 小・中学校再編の進め方について
令和6年6月に設置した気仙沼市小中学校再編検討委員会が中間報告の取りまとめ作業に入り、具体的な再編案について保護者や市民から意見聴取する段階に進む見込みとなりました。再編計画の決定に向けて重要な局面に入ることから、建設的な議論に発展することを期待して、次の5点について市の考えを伺います
(1)気仙沼市小中学校再編検討委員会に諮問したのは、「再編の基本的な考え方」「具体的な学校配置案」「今次再編後の考え方」「再編整備の具体的な方策」「その他の必要事項」の5項目です。中間報告は3月中に取りまとめる予定ですが、検討委員会を傍聴していて「今次再編後の考え方」と「再編整備の具体的な方策」について議論が不足していると感じました。この2項目を諮問事項に入れた理由と現在の検討状況を伺います
(2)事務局がたたき台として示した中学校を4校に再編する配置案について、検討委員会は「妥当」としましたが、最短で令和9年度、10年度と想定する時期については準備期間への不安から慎重論も出ています。特に階上、面瀬、松岩の3中学校の再編については、1学年最大5クラスと現校舎に入りきらない規模であり、仮設校舎などのデメリットの面も心配されることから、段階的な再編の可能性を含めた慎重な検討が求められます。4月以降に保護者や地域へ説明する際の注目ポイントにもなりますので、「3校同時再編」と「段階的な再編」について教育委員会が考えるメリットとデメリットを伺います
(3)小・中学校の再編の議論と並行して、スクールバスをはじめとする通学費用について、市がどこまで覚悟できるか示していく考えが明らかにされていましたが、中間報告には間に合いますか。現在の検討状況について伺います
(4)合意形成に時間と労力を要した前再編計画の教訓は、計画策定の段階で市民の理解をしっかりと得て、決まったらなるべく早く実行に移すとのことでした。理解を得るためには、メリットだけでなくデメリットについても整理して十分な検討材料を揃えること、再編ではなくても解決できることを混同させないこと、地域への影響について考慮すること、意見を出しやすい環境をつくること、住民同士で話し合いの機会をつくることが大切だと思います。市民理解の醸成に向けた取組と考え方を伺います
(5)中学校を4校に再編することが現実となれば、道路をはじめとするインフラ整備、交通・住宅政策、地域コミュニティにも影響を及ぼすことが考えられます。小中学校再編計画の策定作業と並行して、学校教育以外への影響と今後の対応について考える場が必要と思いますが、市の考えを伺います