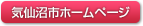録画中継再生
※本会議の録画映像をご覧いただけます。
- 令和7年第146回(6月)定例会 6月24日 本会議 一般質問
- 創生けせんぬま 熊谷 伸一 議員
eyJwbGF5ZXJLZXkiOiJjYmJlMDljOS0yYzc0LTQwNDEtOWJkNC1iYjZlY2UzYjk0MDAiLCJhbmFseXRpY3NLZXkiOiI5ZWM4YTVlMS1lNWNkLTRkMzUtYTFlMC0wOTE4MWYzOTQwMDYiLCJpc0xpdmUiOmZhbHNlLCJ0aXRsZSI6Imtlc2VubnVtYS1jaXR5XzIwMjUwNjI0XzAwNDBfa3VtYWdhaS1zaGluaWNoaSIsInBsYXllclNldHRpbmciOnsicG9zdGVyIjoiLy9rZXNlbm51bWEtY2l0eS5zdHJlYW0uamZpdC5jby5qcC9pbWFnZS90aHVtYm5haWwuZml4LmpwZyIsInNvdXJjZSI6Ii8va2VzZW5udW1hLWNpdHkuc3RyZWFtLmpmaXQuY28uanAvP3RwbD1jb250ZW50c291cmNlJnRpdGxlPWtlc2VubnVtYS1jaXR5XzIwMjUwNjI0XzAwNDBfa3VtYWdhaS1zaGluaWNoaSZpc2xpdmU9ZmFsc2UiLCJjYXB0aW9uIjp7ImVuYWJsZWQiOiJmYWxzZSIsInBhdGgiOiIifSwidGh1bWJuYWlsIjp7ImVuYWJsZWQiOiJmYWxzZSIsInBhdGgiOiIifSwibWFya2VyIjp7ImVuYWJsZWQiOiJmYWxzZSIsInBhdGgiOiIifSwic3BlZWRjb250cm9sIjp7ImVuYWJsZWQiOiJ0cnVlIiwiaXRlbSI6WyIwLjUiLCIwLjc1IiwiMSIsIjEuMjUiLCIxLjUiLCIyIl19LCJza2lwIjp7ImVuYWJsZWQiOiJ0cnVlIiwiaXRlbSI6WzEwLDMwXX0sInN0YXJ0b2Zmc2V0Ijp7ImVuYWJsZWQiOiJmYWxzZSIsInRpbWVjb2RlIjowfSwic2Vla2JhciI6InRydWUiLCJzZHNjcmVlbiI6ImZhbHNlIiwidm9sdW1lbWVtb3J5IjpmYWxzZSwicGxheWJhY2tmYWlsc2V0dGluZyI6eyJTdGFsbFJlc2V0VGltZSI6MzAwMDAsIkVycm9yUmVzZXRUaW1lIjozMDAwMCwiUGxheWVyUmVsb2FkVGltZSI6MzAwMCwiU3RhbGxNYXhDb3VudCI6MywiRXJyb3JNYXhDb3VudCI6M319LCJhbmFseXRpY3NTZXR0aW5nIjp7ImN1c3RvbVVzZXJJZCI6Imtlc2VubnVtYS1jaXR5IiwidmlkZW9JZCI6Imtlc2VubnVtYS1jaXR5X3ZvZF8xNDExIiwiY3VzdG9tRGF0YSI6eyJlbnRyeSI6InB1YmxpYyJ9fX0=
◎一問一答
1 「ポスト震災後の経済白書」について
本市は、急速な少子高齢化という難題と向き合いつつ、この美しいふるさとで心豊かに暮らせる社会を継続させていくため、先進的な施策を展開しつつ、人口減少対策のための行動計画「けせんぬまWell-beingプラン2024」に取り組んでいます。来年度には、大島・亀山モノレールの開業を予定しており、観光都市・気仙沼の魅力をより高めることが期待され、まさに復興の最終局面にあるといえます。東日本大震災から15年目という節目を迎えるいま、菅原市政の4期目も残すところ1年を切りました。「ポスト震災後」という、また新たな時代へと舵を切る、「気仙沼丸」の船長兼船頭としてどういう方針を打ち出すのでしょうか。5期目に挑むのであれば、市役所移転前後の市政を担うことになります。新たなまちが動き出し、市内の交流人口の中心が、内湾地区から条南地区へと移行することが想定されます。今後を見据えたビジョンを市民に対し明確に示すことが求められると考えます。将来のビジョンは、菅原市政の「白書」ともいえるでしょう。「白書」とは「現状分析と将来展望を示す報告書」です。ポスト震災後の現在地にいる気仙沼市長としての「経済白書」を示していただきたく、率直な現状分析と本市の将来展望について伺います
2 「将来を見据えた気仙沼の観光戦略」について
(1)観光庁は、「観光はコロナ禍を経ても成長戦略の柱、地域活性化の切り札である」として、第4次観光立国推進基本計画の中で、観光立国の持続可能な形での復活に向け、観光の質的向上を象徴とする「持続可能な観光」「消費額拡大」「地方誘客促進」の3つをキーワードに、持続可能な観光地域づくり、インバウンド回復、国内交流拡大の3つの戦略に取り組むとしていますが、本市の将来を見据えた観光戦略を伺います
(2)市役所の条南地区への移転が与える影響は、昼間人口が大きく減少することが見込まれるため、「観光の顔」を抱える内湾一帯を含む、中心市街地の再構築は必須と言えます。そこを怠れば、この地域は衰退し、最終的には気仙沼全体の弱体化へと直結します。「三日町八日町・市役所跡地検討ワーキング・グループ」において、議論を重ね、観光振興策を含めた具体的なアイデアが検討されていますが、市として観光視点を含めた内湾地区の再構築をどのように捉え、計画しているのか伺います
(3)気仙沼市内に残る数少ない木造建築である現市役所第二庁舎の利活用について伺います。内湾入口駅に隣接する第二庁舎の一部を「駅舎」として活用する可能性もあるのではないかと考えます。「内湾入口駅から内湾地区への動線の確保」という視点から見ても、極めて親和性の高い案になりうると考えます。市役所跡地が交通のハブとして、さまざまな市内観光コースが楽しめる拠点、まさに「駅」の役割を担うものと期待しますが、可能性、課題について伺います
(4)気仙沼市の将来を見据えた時、市が経営に参画し、共に金銭的なリスクを負う立場を広く、明確に示すことが必要であると考えます。今更「3セク」か、と疑問を抱くかもしれませんが、職員にコスト意識と成果を「肌で知る」貴重な機会になるはずです。お互いに緊張感のある経営感覚を共有する意味でも、「創るのは市、やるのは民」ではなく、「市」と「民」、まさに「市民」で創造する喜びを共有する持続可能なまちづくり、観光都市にしたいものと考えますが、所見を伺います
3 子どもの発達支援と5歳児健診の早期実施について
(1)先日開催した議会報告会、市民と議員の意見交換会において活発な意見交換がありました。障害と子育てという視点では、ハンディを抱える子どもを持つ親の相談窓口、情報の不足や子どもたちの障害の特性に応じたサポート不足などが指摘されました。本市として、庁内における連携体制、保護者が抱える不安や不満への支援体制、そして愛知県岡崎市こども発達支援センターの取組をどのように捉え、今後の施策にとのように反映させていくのか伺います
(2)昨年12月定例会の一般質問において5歳児健診の必要性と実施を求めた質問に対し、積極的に調査研究していくとの答弁でした。一方、今年に入って、こども家庭庁から、令和10年度までに全国の自治体で5歳児健診の実施を目指すとして、支援強化を打ち出しています。この5歳児健診の役割は、発達障害のある子どもを探すことではなく、子どもの状態に応じて、保護者が支援の必要性を理解すること、就学後に本人が学校に適応していくために重要で、地域が子どもたちを支援する体制を作るためにも、この制度を定着させる意義は大きいと指摘されます。本市の5歳児健診の早期実施について、具体的な調査研究内容、実施までのスケジュールを伺います
1 「ポスト震災後の経済白書」について
本市は、急速な少子高齢化という難題と向き合いつつ、この美しいふるさとで心豊かに暮らせる社会を継続させていくため、先進的な施策を展開しつつ、人口減少対策のための行動計画「けせんぬまWell-beingプラン2024」に取り組んでいます。来年度には、大島・亀山モノレールの開業を予定しており、観光都市・気仙沼の魅力をより高めることが期待され、まさに復興の最終局面にあるといえます。東日本大震災から15年目という節目を迎えるいま、菅原市政の4期目も残すところ1年を切りました。「ポスト震災後」という、また新たな時代へと舵を切る、「気仙沼丸」の船長兼船頭としてどういう方針を打ち出すのでしょうか。5期目に挑むのであれば、市役所移転前後の市政を担うことになります。新たなまちが動き出し、市内の交流人口の中心が、内湾地区から条南地区へと移行することが想定されます。今後を見据えたビジョンを市民に対し明確に示すことが求められると考えます。将来のビジョンは、菅原市政の「白書」ともいえるでしょう。「白書」とは「現状分析と将来展望を示す報告書」です。ポスト震災後の現在地にいる気仙沼市長としての「経済白書」を示していただきたく、率直な現状分析と本市の将来展望について伺います
2 「将来を見据えた気仙沼の観光戦略」について
(1)観光庁は、「観光はコロナ禍を経ても成長戦略の柱、地域活性化の切り札である」として、第4次観光立国推進基本計画の中で、観光立国の持続可能な形での復活に向け、観光の質的向上を象徴とする「持続可能な観光」「消費額拡大」「地方誘客促進」の3つをキーワードに、持続可能な観光地域づくり、インバウンド回復、国内交流拡大の3つの戦略に取り組むとしていますが、本市の将来を見据えた観光戦略を伺います
(2)市役所の条南地区への移転が与える影響は、昼間人口が大きく減少することが見込まれるため、「観光の顔」を抱える内湾一帯を含む、中心市街地の再構築は必須と言えます。そこを怠れば、この地域は衰退し、最終的には気仙沼全体の弱体化へと直結します。「三日町八日町・市役所跡地検討ワーキング・グループ」において、議論を重ね、観光振興策を含めた具体的なアイデアが検討されていますが、市として観光視点を含めた内湾地区の再構築をどのように捉え、計画しているのか伺います
(3)気仙沼市内に残る数少ない木造建築である現市役所第二庁舎の利活用について伺います。内湾入口駅に隣接する第二庁舎の一部を「駅舎」として活用する可能性もあるのではないかと考えます。「内湾入口駅から内湾地区への動線の確保」という視点から見ても、極めて親和性の高い案になりうると考えます。市役所跡地が交通のハブとして、さまざまな市内観光コースが楽しめる拠点、まさに「駅」の役割を担うものと期待しますが、可能性、課題について伺います
(4)気仙沼市の将来を見据えた時、市が経営に参画し、共に金銭的なリスクを負う立場を広く、明確に示すことが必要であると考えます。今更「3セク」か、と疑問を抱くかもしれませんが、職員にコスト意識と成果を「肌で知る」貴重な機会になるはずです。お互いに緊張感のある経営感覚を共有する意味でも、「創るのは市、やるのは民」ではなく、「市」と「民」、まさに「市民」で創造する喜びを共有する持続可能なまちづくり、観光都市にしたいものと考えますが、所見を伺います
3 子どもの発達支援と5歳児健診の早期実施について
(1)先日開催した議会報告会、市民と議員の意見交換会において活発な意見交換がありました。障害と子育てという視点では、ハンディを抱える子どもを持つ親の相談窓口、情報の不足や子どもたちの障害の特性に応じたサポート不足などが指摘されました。本市として、庁内における連携体制、保護者が抱える不安や不満への支援体制、そして愛知県岡崎市こども発達支援センターの取組をどのように捉え、今後の施策にとのように反映させていくのか伺います
(2)昨年12月定例会の一般質問において5歳児健診の必要性と実施を求めた質問に対し、積極的に調査研究していくとの答弁でした。一方、今年に入って、こども家庭庁から、令和10年度までに全国の自治体で5歳児健診の実施を目指すとして、支援強化を打ち出しています。この5歳児健診の役割は、発達障害のある子どもを探すことではなく、子どもの状態に応じて、保護者が支援の必要性を理解すること、就学後に本人が学校に適応していくために重要で、地域が子どもたちを支援する体制を作るためにも、この制度を定着させる意義は大きいと指摘されます。本市の5歳児健診の早期実施について、具体的な調査研究内容、実施までのスケジュールを伺います