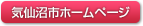録画中継再生
※本会議の録画映像をご覧いただけます。
- 令和7年第146回(6月)定例会 6月25日 本会議 一般質問
- 未来の風 今川 悟 議員
eyJwbGF5ZXJLZXkiOiJjYmJlMDljOS0yYzc0LTQwNDEtOWJkNC1iYjZlY2UzYjk0MDAiLCJhbmFseXRpY3NLZXkiOiI5ZWM4YTVlMS1lNWNkLTRkMzUtYTFlMC0wOTE4MWYzOTQwMDYiLCJpc0xpdmUiOmZhbHNlLCJ0aXRsZSI6Imtlc2VubnVtYS1jaXR5XzIwMjUwNjI1XzAwMTBfaW1ha2F3YS1zYXRvcnUiLCJwbGF5ZXJTZXR0aW5nIjp7InBvc3RlciI6Ii8va2VzZW5udW1hLWNpdHkuc3RyZWFtLmpmaXQuY28uanAvaW1hZ2UvdGh1bWJuYWlsLmZpeC5qcGciLCJzb3VyY2UiOiIvL2tlc2VubnVtYS1jaXR5LnN0cmVhbS5qZml0LmNvLmpwLz90cGw9Y29udGVudHNvdXJjZSZ0aXRsZT1rZXNlbm51bWEtY2l0eV8yMDI1MDYyNV8wMDEwX2ltYWthd2Etc2F0b3J1JmlzbGl2ZT1mYWxzZSIsImNhcHRpb24iOnsiZW5hYmxlZCI6ImZhbHNlIiwicGF0aCI6IiJ9LCJ0aHVtYm5haWwiOnsiZW5hYmxlZCI6ImZhbHNlIiwicGF0aCI6IiJ9LCJtYXJrZXIiOnsiZW5hYmxlZCI6ImZhbHNlIiwicGF0aCI6IiJ9LCJzcGVlZGNvbnRyb2wiOnsiZW5hYmxlZCI6InRydWUiLCJpdGVtIjpbIjAuNSIsIjAuNzUiLCIxIiwiMS4yNSIsIjEuNSIsIjIiXX0sInNraXAiOnsiZW5hYmxlZCI6InRydWUiLCJpdGVtIjpbMTAsMzBdfSwic3RhcnRvZmZzZXQiOnsiZW5hYmxlZCI6ImZhbHNlIiwidGltZWNvZGUiOjB9LCJzZWVrYmFyIjoidHJ1ZSIsInNkc2NyZWVuIjoiZmFsc2UiLCJ2b2x1bWVtZW1vcnkiOmZhbHNlLCJwbGF5YmFja2ZhaWxzZXR0aW5nIjp7IlN0YWxsUmVzZXRUaW1lIjozMDAwMCwiRXJyb3JSZXNldFRpbWUiOjMwMDAwLCJQbGF5ZXJSZWxvYWRUaW1lIjozMDAwLCJTdGFsbE1heENvdW50IjozLCJFcnJvck1heENvdW50IjozfX0sImFuYWx5dGljc1NldHRpbmciOnsiY3VzdG9tVXNlcklkIjoia2VzZW5udW1hLWNpdHkiLCJ2aWRlb0lkIjoia2VzZW5udW1hLWNpdHlfdm9kXzE0MTciLCJjdXN0b21EYXRhIjp7ImVudHJ5IjoicHVibGljIn19fQ==
◎一問一答
1 ふるさと納税の活用とルール遵守について
本市はふるさと納税による寄附金を未来への投資に活用し、様々な施策を展開していますが、もっと目に見える使い方も必要だと思います。一方で、他自治体ではルール違反によって指定取り消しに至ってしまう事例もあり、好調な時ほど管理体制にも力を入れなければなりません。そこで、次の3点について質問します
(1)ふるさと納税寄附金は「人口減少対策」「教育」に加えて、「産業」のパッケージへ充当する方針ですが、今後もパッケージを基本とする考えなのでしょうか。また、市民からアイデアを募って活用する枠の創設、そして令和6年6月の一般質問でも取り上げた高齢化社会へ対応するための活用など、子どもや産業だけではない分野、もっと目に見える形での活用について市の考えをあらためて伺います
(2)ふるさとや応援したい地域に寄附する制度の意義からすると、寄附を活用した施策の成果を積極的に示し、感謝の気持ちを伝えることも大切です。現在は市ホームページで活用実績を発信していますが、もっと感謝の気持ちを表す内容にしたり、寄附を活用した施設に感謝の気持ちを表示したりする考えはありませんか。返礼品を提供する事業所への恩恵をはじめとする地域経済効果について情報発信することも含めて、市の考えを伺います
(3)寄附額の増加に期待が高まる中、ルール違反によって指定取り消しになり、大きな影響を受ける自治体も出現しています。本市でも十分に気を付けているとのことですが、返礼品の品質や配送遅延などに対する苦情は発生していませんか。また、物価高騰等による返礼品事業者への影響を伺います。なお、産地判別のために専門機関を活用した抜き打ち検査を実施している自治体もありますが、本市でのチェック・管理体制の現状と課題、独自ルールの設定状況について伺います
2 公費で発生するポイントについて
個人所有のポイントカードやクレジットカードを公務で使用した際のポイントの不適切な処理が全国的な問題となり、本市でも対応が始まっているようです。私的に過剰な利益を得ないためのルール作りは必要ですが、行き過ぎた対応はキャッシュレス時代に逆行し、不便を生じさせることになりますので、次の2点について質問します
(1)物品の購入や出張時におけるポイントの発生や取得に対し、本市の現状とルールの内容、その課題を伺います
(2)高齢介護課の交流サロン事業は、助成金を使用する際、現金での支払いとともにポイントカードを使用しないよう通知しました。市の補助金や助成金を受けている団体について、ポイントの発生と取得に関するルールの内容と課題を伺います
3 小中学校再編検討委員会の中間報告について
小中学校再編検討委員会の中間報告が公開され、保護者や地域住民向けに説明会が行われました。6月23日までパブリックコメントを実施し、今後は最終検討に進み、8月の答申、9月の再編整備計画決定が予定されています。市の将来に影響する重要な計画ですが、地域に諦めムードが漂う中、市民による議論が十分だとは感じられません。そこで、私が疑問に感じている次の5点について質問します
(1)中間報告の説明会では「決定事項の説明になっている」「意見を言えば見直されるのか」という参加者の意見に対し、教育委員会からの否定的な回答が気になりました。本来なら、意見を検討委員会に伝えることが事務局の役割だと思います。検討委員会と教育委員会の役割について、教育長の考えを伺います
(2)中学校9校を4校に再編する案を実現するためには、単純計算で最大475人(受け入れ校以外の令和10年度生徒数の合計)のスクールバスを確保するという難題が生じます。これまでの統合によって閉校した学校から令和5年度は211人を対象にスクールバスを運行し、約8千万円を要しました。中間報告通りに統合した場合の必要な車両数とその確保策、費用と財源について検討状況を伺います
(3)統合後のスクールバスや仮設校舎の費用を考えると、その費用で市町村費負担教職員任用制度を活用すれば、少人数学級や学校間連携に取り組んだり、外部人材やスポーツクラブ等への部活動移行を推進したりできると思います。子どもが減るから学校を減らすという対処的な考え方だけでなく、新しい発想でこれからの学校の在り方について考えていく姿勢も必要だと思いますので、教育委員会の考えを伺います
(4)現在の出生数を考慮すると、中学校についてはさらに次の再編が避けられないことが明白です。4校への再編検討と合わせて、もっと踏み込んだ長期的な希望を持てるビジョンを示すことが必要だと思います。再編検討委員会の答申後の役割と合わせて、教育委員会の考えを伺います
(5)中間報告の説明会に参加してみて、指定校変更の現状を市民に伝えるべきだと思いました。傾向を含めた現状、再編との関係性、制度の見直し、今後の情報公開について伺います
1 ふるさと納税の活用とルール遵守について
本市はふるさと納税による寄附金を未来への投資に活用し、様々な施策を展開していますが、もっと目に見える使い方も必要だと思います。一方で、他自治体ではルール違反によって指定取り消しに至ってしまう事例もあり、好調な時ほど管理体制にも力を入れなければなりません。そこで、次の3点について質問します
(1)ふるさと納税寄附金は「人口減少対策」「教育」に加えて、「産業」のパッケージへ充当する方針ですが、今後もパッケージを基本とする考えなのでしょうか。また、市民からアイデアを募って活用する枠の創設、そして令和6年6月の一般質問でも取り上げた高齢化社会へ対応するための活用など、子どもや産業だけではない分野、もっと目に見える形での活用について市の考えをあらためて伺います
(2)ふるさとや応援したい地域に寄附する制度の意義からすると、寄附を活用した施策の成果を積極的に示し、感謝の気持ちを伝えることも大切です。現在は市ホームページで活用実績を発信していますが、もっと感謝の気持ちを表す内容にしたり、寄附を活用した施設に感謝の気持ちを表示したりする考えはありませんか。返礼品を提供する事業所への恩恵をはじめとする地域経済効果について情報発信することも含めて、市の考えを伺います
(3)寄附額の増加に期待が高まる中、ルール違反によって指定取り消しになり、大きな影響を受ける自治体も出現しています。本市でも十分に気を付けているとのことですが、返礼品の品質や配送遅延などに対する苦情は発生していませんか。また、物価高騰等による返礼品事業者への影響を伺います。なお、産地判別のために専門機関を活用した抜き打ち検査を実施している自治体もありますが、本市でのチェック・管理体制の現状と課題、独自ルールの設定状況について伺います
2 公費で発生するポイントについて
個人所有のポイントカードやクレジットカードを公務で使用した際のポイントの不適切な処理が全国的な問題となり、本市でも対応が始まっているようです。私的に過剰な利益を得ないためのルール作りは必要ですが、行き過ぎた対応はキャッシュレス時代に逆行し、不便を生じさせることになりますので、次の2点について質問します
(1)物品の購入や出張時におけるポイントの発生や取得に対し、本市の現状とルールの内容、その課題を伺います
(2)高齢介護課の交流サロン事業は、助成金を使用する際、現金での支払いとともにポイントカードを使用しないよう通知しました。市の補助金や助成金を受けている団体について、ポイントの発生と取得に関するルールの内容と課題を伺います
3 小中学校再編検討委員会の中間報告について
小中学校再編検討委員会の中間報告が公開され、保護者や地域住民向けに説明会が行われました。6月23日までパブリックコメントを実施し、今後は最終検討に進み、8月の答申、9月の再編整備計画決定が予定されています。市の将来に影響する重要な計画ですが、地域に諦めムードが漂う中、市民による議論が十分だとは感じられません。そこで、私が疑問に感じている次の5点について質問します
(1)中間報告の説明会では「決定事項の説明になっている」「意見を言えば見直されるのか」という参加者の意見に対し、教育委員会からの否定的な回答が気になりました。本来なら、意見を検討委員会に伝えることが事務局の役割だと思います。検討委員会と教育委員会の役割について、教育長の考えを伺います
(2)中学校9校を4校に再編する案を実現するためには、単純計算で最大475人(受け入れ校以外の令和10年度生徒数の合計)のスクールバスを確保するという難題が生じます。これまでの統合によって閉校した学校から令和5年度は211人を対象にスクールバスを運行し、約8千万円を要しました。中間報告通りに統合した場合の必要な車両数とその確保策、費用と財源について検討状況を伺います
(3)統合後のスクールバスや仮設校舎の費用を考えると、その費用で市町村費負担教職員任用制度を活用すれば、少人数学級や学校間連携に取り組んだり、外部人材やスポーツクラブ等への部活動移行を推進したりできると思います。子どもが減るから学校を減らすという対処的な考え方だけでなく、新しい発想でこれからの学校の在り方について考えていく姿勢も必要だと思いますので、教育委員会の考えを伺います
(4)現在の出生数を考慮すると、中学校についてはさらに次の再編が避けられないことが明白です。4校への再編検討と合わせて、もっと踏み込んだ長期的な希望を持てるビジョンを示すことが必要だと思います。再編検討委員会の答申後の役割と合わせて、教育委員会の考えを伺います
(5)中間報告の説明会に参加してみて、指定校変更の現状を市民に伝えるべきだと思いました。傾向を含めた現状、再編との関係性、制度の見直し、今後の情報公開について伺います